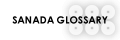
 |
| 【海野平合戦】 | 天文10年(1541) |
海野一族が、武田・諏訪・村上の連合軍に攻められて敗北。 幸隆も上州へ敗走したが、まもなく武田家に仕官している。 |
| 【上田原合戦】 | 天文17年(1548)2月 |
武田信玄は、諏訪・佐久地方を平定した後、村上義清が支配する北信濃へ侵攻、上田原で衝突した。
20日に及ぶ激戦の末、武田軍は退却。武田信玄が初めて敗北した戦いとなる。 真田幸隆も武田方の武将として参戦している。 |
| 【砥石崩れ】 | 天文19年(1550)9月 |
武田信玄は、信濃守護小笠原氏を滅ぼし信濃国内での勢力を回復。
北信への勢力拡大を目論み、村上義清留守中の戸石城を攻める。
しかし、戸石城は落ちず撤退。村上義清の猛追撃を受けて大敗を喫す。 翌年、真田幸隆が独力で砥石城を落とし(「高白斎記」に「砥石ノ城真田乗取」とだけ記してある)、これによって幸隆は真田旧領を回復した。 |
| 【川中島合戦】 |
永禄4年(1561) 第4次川中島合戦 |
上杉謙信(長尾景虎)と武田信玄の戦い。 武田勢は山本勘助が献策した「啄木鳥戦法」を 謙信に見破られ、逆に奇襲を受けて苦戦。 上杉勢の撤退で引き分けに終わったものの、 武田勢は武田信繁・山本勘助らが討ち死にした。 この合戦には、真田幸隆・真田信綱・真田昌幸が参戦、 昌幸はこれが初陣という説も。 |
| 【長篠合戦】 | 天正3年(1575)5月 |
三河国長篠城を攻めた武田勝頼軍と、長篠救援に駆けつけた織田・徳川連合軍が
設楽原で衝突した。織田軍3000挺の鉄砲隊の前に武田騎馬軍は壊滅。 この戦いで、真田信綱・昌輝兄弟が討死した。 |
| 【第一次上田合戦】 |
天正13年(1585)8月 別称:神川合戦 |
真田昌幸は徳川家からの沼田領引渡し要求を拒否。 徳川家の攻撃を受けたが、これを退ける。 |
| 【小田原の役】 | 天正18年(1590) | 真田家と北条家の沼田を巡る争いを契機に、秀吉が小田原攻めの軍を起こす。 これにより北条家は滅亡、豊臣秀吉の天下統一が成る。 |
| 【文禄慶長の役】 |
文禄元年(1592) -慶長2年(1597) |
秀吉の命により昌幸父子も朝鮮出兵。 戦後、秀吉より恩賞として三原の太刀を拝領。 |
| 【関ヶ原の合戦】 |
慶長5年(1600) 9月15日 |
全国の諸大名が、豊臣家に代わって天下を狙う徳川家康(東軍)と、
それを阻止しようとする石田三成ら(西軍)とに分かれ、
総勢20万もの大軍が美濃関ヶ原で衝突した合戦。 真田家では、昌幸・信繁が西軍、信幸らが東軍につく。 |
| 【第二次上田合戦】 |
慶長5年(1600) 9月2日−6日 |
西軍についた昌幸らは上田城に籠城。 関ヶ原を目指す徳川秀忠の軍勢を挑発して 4日の間、秀忠の軍勢を釘付けにした。 秀忠は上田攻略を諦めたが、 ついに関ヶ原合戦には間に合わなかった。 |
| 【大坂冬の陣】 |
慶長19年(1614) 10月-12月 |
天下人の座を奪われた豊臣家が、徳川家康の挑発に乗って挙兵。 関ヶ原に敗れた浪人10万を大坂城に集めて籠城する。 九度山に蟄居していた真田信繁も10月に入城。 大坂城の弱点となっていた南側に出城(真田丸)を築いて徳川軍と対決し、 前田・井伊・藤堂らの軍勢をさんざんに叩く。 この戦いでの活躍で、真田信繁の武名が天下に轟くことになった。 |
| 【大坂夏の陣】 |
慶長20年(1615) 5月7日 |
冬の陣が和議を結んで終了したのち、徳川軍は
講和条件を破って大坂城の堀を埋め立てる。
これに抗議した豊臣家に対して、徳川家が再び出兵。
激戦の末、大坂城は炎上し、豊臣家は滅亡した。 この戦いで、真田信繁は徳川軍を猛烈に攻め立てるが 奮戦むなしく討死。真田大助も豊臣秀頼に殉じた。 |
TOP /
PERSONS /
CASTLES /
LETTERS /
ET CETERA
2003 / COPYRIGHT / R-HAYASHI