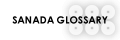
 |
| あ − か |
| 【上田城】 |
長野県上田市 天正11年(1583)築城 別名:尼ヶ淵城 |
真田昌幸の居城。 千曲川を天然の堀とする平城。本丸、二の丸、三の丸に水堀、さらに捨郭として小泉郭が西に置かれる。 天正13年(1585)と慶長5年(1600)の二度に渡り、徳川軍の攻撃を退けた。 | 【岩尾城】 | 長野県佐久市 | 真田幸隆が、武田家に出仕して間もなくの頃、城代を勤めたと伝わる。 |
| 【岩櫃城】 |
群馬県吾妻郡 |
もとの城主は、上杉家・斎藤越前守憲弘。 永禄6年(1563)、幸隆は敵方の海野兄弟を内応させ、斎藤憲弘・羽尾幸全を破って攻略。 その後真田氏の吾妻郡支配の拠点となる。 |
| 【大坂城】 |
大阪府大阪市中央区大阪城 天正11年(1583)築城開始 |
豊臣秀吉が石山本願寺跡地に本拠として築城。 秀吉没後、徳川家と対立した豊臣家の要請により、九度山蟄居中であった真田信繁が入城。 大坂城の弱点とされた三の丸南側玉造口付近に出城「真田丸」を築いて徳川勢と対決。 |
| 【海津城】 |
長野県長野市松代町 永禄3年(1560)築城 |
松代転封ののち、真田家の居城となった松代城の前身。 武田信玄の命により山本勘助が築城、真田幸隆も普請に携わったというが詳細不明。 武田家の北信最前基地となる。 永禄4年(1561)の第4次川中島の合戦の 際には武田信玄の本陣となり、妻女山に陣取る上杉謙信と対峙。 その後は、名将・高坂弾正昌信が守った。 |
| 【小諸城】 |
長野県小諸市 |
天文12(1543)年、武田信玄が攻略。のち武田家の北信濃攻略拠点となる。
武田家滅亡後は仙石氏の居城。第二次上田合戦では徳川秀忠軍が駐留した。 のち「懐古園」として公園整備。 |
| さ − た |
| 【真田本城】 | 長野県小県郡真田町 |
上田築城以前の真田氏の本拠とされる。 真田郷に数多くある城の1つで、平素の住まいとしていた真田氏館に最も近い場所にある城。 |
| 【白井城】 |
群馬県北群馬郡子持村白井 |
白井長尾氏の居城。元亀3年(1572)、真田幸隆により攻略され、武田の属城となる。 真田昌幸が一時期城代を務めていた。 |
| 【新府城】 |
山梨県韮崎市 天正9(1581)年築城 |
武田勝頼が築城。真田昌幸が普請奉行を勤めたと伝わる。 |
| 【洗馬城】 |
長野県小県郡真田町 |
もとは曲尾氏の城であったが、真田幸隆の頃に攻略され、真田郷の支城群の1つに加えられた。 |
| 【戸石城】 |
長野県上田市上野 別称:砥石城 |
村上家の小県拠点。桝形城・本城・戸石城・米山城からなる。 天文19(1550)年、武田軍が攻めるも敗北。 翌天文20年、真田幸隆がこの城の乗っ取りに成功し、 恩賞として武田家より諏訪形(上田市)と上条(不明)に千貫文の地を得る。 |
| な − は |
| 【長篠城】 |
愛知県南設楽郡鳳来町 |
信濃と三河をつなぐ要地。今川→徳川→武田と所属を替え、武田信玄没後に徳川家康が奪還する。 天正3年、長篠城を再び落とすため武田勝頼が出陣し、織田・徳川連合軍と衝突。 この「長篠合戦」は武田軍の惨敗に終わり、真田信綱・昌輝が討死した。 |
| 【名胡桃城】 |
群馬県利根市 天文元(1531)年頃築城 |
真田氏の城で、城代は鈴木主水重利。 名胡桃城が北条家に奪取されたのを機に、秀吉が小田原攻めの軍を起こす。 |
| 【沼田城】 |
群馬県沼田市 天文元(1531)年頃築城 |
沼田氏の居城。 天正8年(1580年)真田昌幸がこれを攻略、北上州一帯を勢力下に置くことに成功した。 のち、真田信幸の居城となり、規模を拡張。 |
| ま − や |
| 【松尾城】 |
長野県小県郡真田町 別称:松尾古城 |
幸隆以前の真田氏の居城。 真田町の北方、角間渓谷の近くにある。 幸隆が武田信玄に仕官したのち復帰。 上田城の別称も「松尾城」と言うが、これは真田氏居城の意味が込められているのかも。 |
| 【丸子城】 | 群馬県群馬郡 |
丸子氏の居城。天正11年(1583)に真田昌幸に攻められ
真田の属城となる。 第一次上田合戦において、真田家に敗れた徳川の軍勢は 鉾先を変えて丸子城を攻撃。城将・丸子三右衛門はよく 守り、徳川勢は落城できぬまま撤退した。 |
| 【箕輪城】 | 群馬県群馬郡 | 海野平合戦後、真田の地を追われた幸隆が、城主長野業正を頼ってしばらく滞在した。 永禄9年(1566年)真田幸隆を含む武田軍が攻略。業正は自刃。 |
| 【矢沢城】 | 長野県上田市 |
矢沢頼綱・頼康らの居城。 第一次上田合戦では、頼康が籠城して善戦。 |
TOP /
PERSONS /
BATTLES /
LETTERS /
ET CETERA
2003 / COPYRIGHT / R-HAYASHI