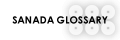
 |
||||
| あ − か | さ − た | な − は | ま − や | ら − わ |
| あ − か | ||
| 【青江の太刀】 |
真田信綱の愛刀。
天正三(1575)年の長篠合戦で、信綱はこの太刀を振るって奮戦するが、
織田・徳川軍の鉄砲隊に撃たれ戦死。
太刀は、家臣・白川勘解由が信州に持ち帰り、代々真田家の宝物として伝承された。
長さ 103cm。延文六(1361)年の作。 現在は重要文化財に指定されており、長野市松代の真田宝物館蔵。 | |
| 【赤備え】 |
武田家の飯富虎昌・山県昌景が具足を赤で統一したのが始まり。
敵・味方の判別と、敵の威嚇が目的と言われる。 真田家の兵士も甲冑を赤で統一し「真田の赤備え」と称された。 武田の遺臣を多く用いた徳川家臣・井伊直政の赤備えも有名。 | |
| 【上田】 |
信濃東部の地名。現在の長野県上田市。 真田昌幸がここに上田城を築城し本拠とした。 | |
|
【安智羅明神】 あんちら-みょうじん |
真田一族の屋敷跡に近い、角間渓谷の社に安置されている像。 幸村の幼少時代の像と伝わるが、由緒は不明。 | |
|
【四阿山】 あずまやさん |
真田町と嬬恋村の境にあり、真田郷を囲む連山の最高峰。 古くより神の山として真田の人々の信仰の対象となっていた。 | |
|
【海野氏】 うんのし |
信州豪族・滋野氏の本家。 滋野三氏の本家である。古くは鎌倉幕府の有力な御家人として名があり、東信濃に長くその勢力を保っていたが、海野棟綱の代に、武田信玄に攻められて没落した。 真田氏は海野氏の系統であるが、嫡流ではない。 | |
| 【大塔軍記】 |
応永7年(1400)におきた大塔合戦の記録。 信濃守護小笠原長秀に反抗した信濃国人衆のうち、禰津氏を中心とする大文字一揆の中に「実田」の名があり、これが真田氏の初見とされる。 | |
| 【海禅吉祥寺】 |
上田城の鬼門除の寺。 保命水水源。 | |
| 【角間渓谷】 |
真田一族の屋敷跡や、かつての真田氏の居城・松尾城に近い渓谷。 岩肌の見える険しい山々が切り立ち、鬼や天狗が住んでいた伝説も残る。 猿飛佐助が修行したとも。 | |
| 【加沢記】 |
沼田藩五代藩主真田信利の家臣・加沢平治左衛門の手記。 真田家が沼田に地盤を固めてゆく過程(天文10年〜天正18年)が記述されている。 | |
| 【鎌原氏】 |
海野氏の庶流。真田幸隆の弟・幸定が養子に入っている。 武田家に仕え、幸定の孫?の重澄は長篠合戦で討死。 重澄の子・重春は真田家に仕えて、昌幸の養女を妻にしている。 | |
|
【肝煎】 きもいり |
真田信幸が置いた大代官の名称。 広域の郡奉行。昌幸が置いたかは不明。 | |
| 【九度山】 | 関ヶ原合戦後、西軍についた真田昌幸・信繁父子が蟄居していた場所。 現在の和歌山県伊都郡九度山町。 | |
|
【虚空蔵山】 こくぞうさん | 砥石城の支城「伊勢崎砦」が築かれた場所。 第二次上田合戦の際には、ここに真田昌幸が伏兵を潜ませ、 徳川秀忠の軍勢の挟撃に成功。秀忠が上田攻略を諦める要因となる。 | |
| さ − た | ||
| 【宰相山公園】 | 大坂冬の陣の際、加賀宰相前田家の陣が置かれた場所。 現在はその一角に三光神社があり、真田幸村の像と「真田の抜け穴跡」がある。 | |
| 【真田石】 |
 上田城本丸東虎口櫓門の正面右手の石垣にある。
真田昌幸が太郎山より切り出して城の礎石とした。
真田信之が松代転封の際に持ち運ぼうとしたが、
大勢の手によってもびくともしなかったと伝わる。
上田城本丸東虎口櫓門の正面右手の石垣にある。
真田昌幸が太郎山より切り出して城の礎石とした。
真田信之が松代転封の際に持ち運ぼうとしたが、
大勢の手によってもびくともしなかったと伝わる。 | |
| 【真田井戸】 |
 上田城本丸にある井戸。
上田城本丸にある井戸。井戸の底には太郎山に通じる抜け道があるとの伝説が残る。 | |
| 【真田郷】 |
信州上田北方の地名。現在の長野県小県郡真田町。 真田発祥の地とされる。 | |
| 【真田三代記】 |
元禄期に成立した歴史小説。 真田昌幸・幸村・大助の活躍を描く。 真田十勇士の原型となる人物たちが登場し、 真田の知名度を上げるのに貢献した。 現在読めるのは土橋治重氏が意訳したもの。 | |
| 【真田十勇士】 |
講談に登場する架空の真田配下。
猿飛佐助・霧隠才蔵・穴山小助・海野六郎・
望月六郎・根津甚八・筧十蔵・由利鎌之介・三好青海・三好伊三。 穴山小助は実在? ほかは架空の人物? 江戸中期に書かれた小説『真田三代記』に十勇士の原型となった人物が登場している。 | |
| 【真田騒動】 |
真田信之(信幸)が隠居した後、信政が松代藩二代藩主に着任するが
半年後、信政が早世。
三代藩主に信政の子・幸道(右衛門)を据えようとうする動きに対し、沼田藩主・
信利(信吉の次男)が横槍を入れて悶着が生じ、これを「真田騒動」と呼ぶ。 結局、信之のとりなしで、幸道が無事に相続した。 その後、信利は圧政を直訴され、沼田藩改易を招いている。 | |
| 【真田紐】 |
木綿糸を平たく丈夫に編んだ紐。
刀の下げ緒や柄紐として使用した。
九度山蟄居中の真田昌幸が考案し、
生計の足しにするために売っていたらしい。
現在は箱紐(高級な陶芸品などを入れる桐箱にかける紐)として使われている。 寄生虫のサナダムシは、真田紐に似ていることから、その名がある。 | |
| 【真田丸】 |
大坂冬の陣の際に、真田信繁が大坂城の弱点とされた三の丸南側玉造口付近に出城を築き、これを「真田丸」と呼んだ。 | |
| 【真田山公園】 | 真田丸跡地の公園。 | |
| 【滋野通記】 | 滋野一族の伝記。寛政7年(1795)の成立。 | |
| 【滋野氏】 |
信州の豪族。清和源氏の流れとされる。 平安後期に、海野氏(本家)・禰津氏・望月氏の三家に分かれる。 真田氏は海野氏の流れ。 | |
| 【信濃先方衆】 | 武田信玄が支配地を拡げる過程で、新たに家臣に加わった武将たちは「先方衆」として組織された。 真田氏も信濃先方衆に組み入れられ、真田信綱の代には先方衆の旗頭を務めている。 | |
| 【篠山】 | 大坂城に築かれた真田丸近くの丘。 信繁はこの丘を巧みに利用して徳川勢を翻弄した。 | |
| 【白鳥神社】 |
海野宿にある真田家(海野家)の氏神。 祭神は海野氏の始祖貞元親王・善淵王・海野広貞。 松代にも真田信幸が建立した同名の神社がある。 | |
| 【真武内伝】 | 真田氏の史書。享保年間(1716〜1735)に編纂されたもの。 | |
| 【信綱寺】 |
真田信綱を弔うために建立された寺。 弟・昌輝の墓もある。長野県小県郡真田町。 | |
| 【州浜紋】 |
 真田氏が用いた家紋の一つ。
真田氏が用いた家紋の一つ。ほかに「六文銭」「結び雁金」も用いた。 | |
| 【清和源氏】 |
清和天皇の第6皇子貞純親王を祖とする家系を指し、武家の名門とされる。 滋野氏も清和源氏を称したが確証はない。 | |
| 【武田二十四将】 | 武田信玄の家臣を代表する武将。真田幸隆・信綱を含む。 二十四将は後世に名づけられたもので、描かれる絵によって24人の人選はまちまち。 昌輝・昌幸を入れることもある。 | |
| 【太郎山】 | 長野県上田市北部。真田石を切り出した山。 上田城の井戸の中には、太郎山への抜け道が隠されていると伝えられるが不明。 | |
|
【千曲川】 ちくまがわ |
甲斐・武州・信濃の3国の境にある甲武信ヶ岳に源を発し、
上田盆地を貫いて北流、越後(新潟県)に入ると信濃川と呼ばれる。 上田城の南側には「尼ヶ淵」と呼ばれる千曲川の支流があり、 これが天然の堀となっていた。 | |
| 【血染めの陣羽織】 |
真田信綱が長篠合戦で討死した際に着用していたとされる。 現在は、信綱寺蔵。 | |
| 【長谷寺・長国寺】 |
長野県長野市松代町。真田家の菩提寺。 天文16年(1547)真田幸隆が真田郷に「長谷寺」を建立。 のち真田信之の松代転封の際に現在の場所に移転し、寺号を「長国寺」に改める。 元祖長谷寺も、真田町に健在。 | |
| 【戸隠】 |
信州北部にある蕎麦の名所。古くから修験道の盛んな地であり、12世紀末期に木曾義仲の家臣・仁科大助が修験道に伊賀流忍術を合せて戸隠流忍術を成立させた。 真田氏が駆使していた忍者たちの中にも戸隠流の忍者がいたのかもしれない。 | |
| 【鳥居紋】 |
 真田一門・矢沢氏が用いた家紋の一つ。
真田一門・矢沢氏が用いた家紋の一つ。矢沢頼綱が用いたと伝わる鳥居紋の旗指物が今も残っている。 | |
| な − は | ||
| 【日本一の兵】 |
島津藩の『薩藩旧記』の中で、大阪夏の陣の真田信繁の戦いぶりを評した言葉。 「真田日本一の兵(つわもの)、古(いにしえ)よりの物語にもこれなき由」 とある。 | |
| 【禰津氏】 |
祢津・根津とも。 信州豪族・滋野三氏の一つ。 禰津元直の代より武田信玄に臣従。武田家滅亡後は真田家に従った。 | |
| 【昇り梯子の鎧】 | 真田昌幸が、初陣となる第四次川中島合戦の戦功により 武田信玄より賜る。 | |
| 【初花】 | 唐物の名物茶入。大坂夏の陣において、真田幸村の部隊を破った戦功を賞し、 松平忠直が徳川家康より賜る。 | |
| 【表裏比興】 |
豊臣秀吉やその側近が、その書状の中で真田昌幸を評して言ったもの。 表裏があって食えぬ奴というような意味。 昌幸が従属先を上杉・北条・徳川・豊臣とコロコロ変えていたため。 | |
| 【別所温泉】 |
信州上田の温泉場。真田一族も訪れたと思われる。 「石の湯」という温泉は「真田幸村公 隠しの湯」とされている。 | |
| 【芳泉寺】 | 真田信幸夫人・小松殿の墓地がある。 | |
| ま − や | ||
| 【三原の太刀】 |
昌幸が朝鮮出陣の恩賞として秀吉より拝領したもの。
無銘であるが、鎌倉末期から南北朝時代、備後三原の刀匠の作。 長さ(刃渡り)72センチ。現在は長野市松代の真田宝物館蔵。 | |
| 【結び雁金紋】 |
 真田氏が用いた家紋の一つ。
ほかに「六文銭」「州浜」も用いた。
真田氏が用いた家紋の一つ。
ほかに「六文銭」「州浜」も用いた。
| |
| 【望月氏】 |
信州豪族・滋野三氏の一つ。北佐久郡望月を本拠とする。 武田信玄に従って長篠の戦いで嫡流(望月盛時)が討死して断絶するが信玄の甥・信雅が後継。 庶流の者で真田氏に仕えた者も多数。 甲賀五十三家筆頭格の望月家も同族らしい。 | |
| 【矢沢氏】 |
真田郷に隣接する矢沢郷を拠とする地侍。 元は諏訪神氏系の一族という。 幸隆の次男・頼綱が養子に入り家督を継いで以来、真田家の重臣となる。 | |
| 【矢出沢川】 |
 上田城の北面及び西面を流れる川。
上田城の北面及び西面を流れる川。築城に当たってその流路を変えられ、外掘の役割を担った。 | |
|
【山家神社】 やまがじんじゃ |
 白山(四阿山)信仰の社。真田氏からも崇敬を受けていた。
白山(四阿山)信仰の社。真田氏からも崇敬を受けていた。四阿山は真田郷を囲む連山の最高峰で、古くより神の山として崇拝され、白山信仰と結びついた。 山家神社には「四阿山から一切木を切ってはならない」という旨の真田昌幸の文書が残っている。 | |
| 【吉光の御長持】 |
松代藩士が代々大切に保管していた文書箱。 真田信幸が徳川秀忠より拝領した備前長船吉光(短刀)と共に、 武田・豊臣・徳川から真田家が拝領した書状の一部が納められている。 | |
| ら − わ | ||
| 【蓮華定院】 |
紀州高野山にある。 関ヶ原後、高野山配流を命じられた真田父子は、 九度山に移るまでの間、蓮華定院に身を寄せている。 以前より真田家と交流のあった寺院で、真田郷民の宿坊となっていた。 | |
| 【六文銭紋】 |
真田家の家紋。六連銭とも呼ぶ。幸隆の代より使用されたと言われる。 六連銭は、仏道における「六道銭」のこと。 死人を葬るときに、棺桶に入れる「三途の川の渡し賃」 「六道」とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上の 6迷界を意味する。 鎌倉時代に成立した「蒙古襲来絵詞」にも五郎城次郎の指物として「連銭の旗」が描かれており、 真田氏が考案したわけではないらしい。 | |
TOP /
PERSONS /
CASTLES /
BATTLES /
LETTERS
2003 / COPYRIGHT / R-HAYASHI