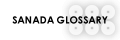
 |
|
真田昌幸宛 織田信長書状 |
天正10年(1582) 4月8日 |
馬一疋黒葦毛、到来、懇志の至り、特に以て馬形・乗り心(のりごこち)以下比類なし。 別して自愛斜めならず候。 はたまた、その面に於て、馳走せしめ候由、尤も然るべく候。 いよいよ情(精)を入れるべきこと専一に候。 猶滝川(一益)申すべく候也。
朱印
佐那田(真田)弾正殿 |
|
真田昌幸宛 長束正家等連名署状 |
慶長5年(1600) 7月17日 |
急度申し入れ候。今度景勝発向の儀、内府公
上巻の誓紙並びに太閤様御置目に背かれ、秀
頼様見捨てられ出馬候の間、おのおの申し談
じ、楯鉾に及び候。
内府公御違ひの条々別紙に相見え候。この旨
尤と思し召し、太閤様の御恩賞を相忘れられ
ず候はば、秀頼様へ御忠節あるべく候。
恐々謹言。
長大 正家(花押)
眞田安房守殿 御宿所増石 長盛(花押) 徳善 玄以(花押) |
|
真田信之宛 徳川家康書状 |
慶長5年(1600) 7月24日 |
今度安房守罷り帰られ候ところ、日比(ひごろ)
の儀を相違へず、立たれ候こと、奇特千万に候。
なほ本多佐渡守申すべく候の間、具(つぶさ)に
する能はず候。
恐々謹言。
家康(花押)
眞田伊豆守殿 |
|
真田信之宛 徳川家康安堵状 |
慶長5年(1600) 7月27日 |
今度安房守別心のところ、その方忠節を致さるる
の儀、誠に神妙に候。然らば、小県の事は親の跡
に候の間、違儀なく遣はし候。その上身上何分に
も取り立つべきの条、その旨を以って、いよいよ
如在に存ぜらるまじく候。仍つて件の如し。
家康(花押)
眞田伊豆守殿
|
|
真田昌幸宛 石田三成書状 |
慶長5年(1600) 7月31日 |
去る廿一日に両度の御使礼、同廿七日に江佐に到来候。拝見候。 一 右の両札の内、御使者持参の書に相添ふ覚書並びに御使者の口上得心の事 一 先ず以って今度の意趣、兼ねて御知せも申さざる儀、ご立腹余儀なく候。 然れども内府大坂にあるうち、諸侍の心如何にも計り難きに付いて、言発 の儀遠慮仕り畢んぬ。なかんづく、貴殿御事とても公儀御疎略なき御身上 に候の間、世間かくの如き上は、争(いか)でとどこほりこれあるべきか。 いづれも隠密の節も申し入れ候ても、世上成り立たざるに付いては、御一 人御得心候ても詮なき儀と存じ思慮す。但し今は後悔に候。御存分余儀な く候。然れどもその段もはや入らざる事に候。千言万句申し候ても、太閤 様御懇意忘れ思し食されず、只今の御奉公希ふ所に候の事 一 上方の趣、大方御使者見聞候。先ず以っておのおの御内儀方大刑少馳走申 され候の条、御心安かるべく候。増石・長大・徳善も同前に候。我等儀御 使者見られ候ごとく、漸く昨日伏見まで罷り上る躰に候。重ねて大坂の御 宿所へも人を進め候て御馳走申すべく候の事 一 大略別条なく、おのおの無二の覚悟に相見え候の間、御仕置に手間入る儀 これなきの事 一 長岡越中儀、太閤様御逝去巳後、かの仁を徒党の大将に致し、国乱雑意せ しむる本人に候の間、即ち丹後国へ人数差し遣はし、かの居城乗取り、親 父幽斎の在城へ押し寄せ、二の丸まで打ち破りし候のところ、命ばかり赦 免の儀禁中へ付いて御佗言申し候間、一命の儀差し宥され、かの国平均に 相済み、御仕置半ばに候の事 一 当暮来春の間、関東御仕置のため差し遣はさるべく候。仍って九州・四国 南海・山陰道の人数、既に八月中を限り、先ず江州に陣取り並びに来兵糧 米先々へ差し送らるべきの御仕置の事 一 羽肥前儀も、公儀に対し毛頭疎意なき覚悟に候。然りと雖も、老母江戸へ 遣はし候間、内府へ疎略なき分の躰に先ず致し候の間、連々公儀如在に存 ぜず候の条、おのおの御得心候て給ひ候へとの申され分に候の事 一 箇条を持って仰を蒙り候ところ、是また御使者に返答候、またこの方より 条目を以って申す儀、この御使者口上に御得心肝要に候の事 一 この方より三人使者を遣はし候。右のうち一人は貴老返事次第案内者そへ られ、この方へ返し下さるべく候。残る二人は会津への書状ども遣はし候 の条、その方より慥なる者御そへ候て、沼田越に会津へ遣はされ候て給ふ べく候。御在所迄返事持ち来り帰り候はば、またその方より案内者一人御 そへ候て上着待ち申し候の事 一 豆州・左衛門尉殿に、別紙を以って申し入るべく候と雖も、貴殿御心得候 て仰せ達せらるべく候。委曲御使者申し伸べらるべく候。恐惶謹言。
三成(花押)
眞房州 御報
※江佐 … 近江佐和山 |
|
真田信之宛 徳川秀忠書状 |
慶長5年(1600) 8月23日 |
以上 わざわざ啓せしめ候。 仍って明二十四にこの地を罷り立ち、ちいさ形へ相動き候の条、その分御心得 候て、彼の表へ御出張あるべく候。尚大久保相模守・本多佐渡守申すべく候。 恐々謹言。
秀忠(花押)
眞田伊豆守殿
|
|
真田信之宛 同昌幸書状(幸村代筆) |
年次不詳 (九度山蟄居中) 3月25日 |
その許の様子、久々承はらず候の間、半左衛門相下し候。御息災に候哉、承はりた
く候。此の方別儀なく候。御心安かるべく候。但しこの一両年は、年積り候故、気
根草臥れ候。万事この方の儀御察しあるべく候。委細は半左衛門申し達すべく候の
間、具にする能はず候。恐々謹言。
追って、珍しからず候へども、玻璃の盆一つ、同じくとうさん二つこれを進じ候。
安房 昌幸(花押)
豆州 参
※玻璃…ガラス |
TOP /
PERSONS /
CASTLES /
BATTLES /
ET CETERA
2003 / COPYRIGHT / R-HAYASHI